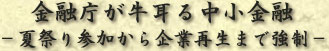|
||||||
|
金融庁を止めてほしい。多くの金融マンはそう思っているに違いない。 11月1日の東京証券取引所の売買システム障害、明治安田生命の保険金不払いと“けしからん”事態が続けば、これらに指導する金融庁の姿勢に、頼もしさを感じる人も多いだろう。 しかし、事態は深層で良くない方向に進んでいる。その方向とは、金融社会主義、すなわち民間金融機関の経営裁量が機能しなくなることだ。
わずか8年間で職員定員が3倍以上になった官庁がある。金融庁だ。国家公務員は減員がこの10年の大方針。130万人にも膨れた官僚天国への国民の潜在的敵意が、郵政民営化も国立大学の法人化も実現させた。そんな中で、金融庁は独り勝ちした。発足以来、幾つかの機関を併合したとはいえ、400人から1,300人への膨張は異例である。1999年から毎年200人、2005年8月にも190人の増員を求めている。 不思議なことだが、金融庁の突出した復活ぶりに異議を唱える者はいなかった。いつも官庁勢力の膨張には反対する民主党をはじめとする野党も、また自由民主党の反・財務省族も黙認したまま事態は“順調”に経過した。 この膨張路線の一環として、主に地方を舞台に、ある事態が進行している。それは全国の中小・地域金融機関を対象にした「リレーションシップバンキング推進行政」(下図を参照)である。
金融界になじみの薄い読者のために少し解説しておこう。リレーションシップバンキング(リレバン)とは金融機関の経営についての指針である。 要は、貸し出しに際して担保の有無に過度にこだわらず、貸出先企業との長い取引関係から得られる情報(いわゆる定性情報)に基づいて貸し出しの判断をすることだ。この言葉の源泉は米国にあり、リレーションシップレンディングと呼ばれることが多い。 では政策の中身を検討してみよう。まずベンチャー企業支援、創業支援だが、この事業は時代の流行のようでもあり、「やって当然」の雰囲気もあるが、10年ほど前には預金者の資金を危険にさらすかもしれない“とんでもない”分野だった。学会でも預金を扱う間接金融機関にどこまでこの分野での活動が可能かは議論がある。 ベンチャー支援にはいくつかの類型がある。まず資金の支援、これは投資と融資に大別される。そして資金以外の支援(コンサルティング、顧客紹介など)。投資については先に述べたように、中小・地域金融機関は慎重であるべきだ。どうしてもやるなら次の2つの方法がある。 1つは、この世界のプロであるベンチャーキャピタルの主宰する投資ファンドに出資する方法だ。しかし、これでは投資のイニシアティブ(主導権)は握れない。いわゆるゼネラルパートナー(執行者)ではないからだ。 第2の方法は自分で投資する方法だが、その際は、別会社にするなどの垣根が必要だ。銀行の融資では1000に1つの失敗も許されないが、投資では極端に言えば10のうち1つ成功すればよい。全く哲学の違う業務が同じ屋根の下にあるのは企業文化の維持にとって問題だろう。両部門の間を職員が頻繁に異動するのも具合が悪い。 融資の精神と投資の精神は違う。目指す頂上は中小企業の育成で同じでも、断崖の北壁を登るのと緩やかな東南の尾根道を行くほどの違いがある。 ベンチャー投資やベンチャー融資をする際には、忘れてならない1つの制約がある。それは、自己資本(資本金+剰余金)の範囲内ということである。借入資本(預金や債券発行)で投資をすることは危険である。 ベンチャー支援の課題との関連で言及されるのが、“目利き能力”というやや怪しい概念である。担保に頼らないで融資を進めるための1つの“能力”が目利きだが、それは「理解できなくても感じることは可能」と言われる。だが、これを養う科学的な方法は今のところない。行政は神秘的なことを言わない方がよい。 ついでに言えば企業再生ビジネスも金融機関だけでは難しい仕事である。不良債権のランクを企業支援で向上させることは必要だし、それを可能にする能力もあるが、傾いてしまった企業を再建するとなると大事である。地方及び中小の金融機関にまだ専門家は少ないし、要員を配置できる機関も多くない。1兆円超の資本金を持ちエリート職員を多数擁する日本政策投資銀行でも事業再生で扱った件数は、2001年から現在までで約20件に過ぎない。地方銀行の多くが再生ファンドに出資しているが、事はたやすくない。
では、地域貢献はどうだろうか。 営利企業であっても社会に、あるいは立地する地域に貢献するのは当然である。ここに異論のある人はいない。問題は、貢献の仕方と、それを監督当局が言い出すことの不自然さである。 最近ではCSR(企業の社会的責任)という言葉が流行しているが、営利企業は利益を上げ、その一部で税金を払うのが第一義的社会的責任である。政府は税金で公共のための仕事をする。公と民の分業が大原則である。 社会貢献をしているかと聞かれて、していないとは答えられない。しかし、実際には困っている。金融機関の指導者の中には、地域貢献と言われて、公園のゴミ拾いや、夏祭りの音頭取りを考えてしまう人も多い。もちろん、金融機関は地域での評判も営業上必要だから、その限りで様々な地域のイベントに協賛する(下表)。しかし、それが彼らの本来の目的でないことは関係者が分かっている。
このような時代錯誤的な要請が監督当局から出てくるのはなぜか。それは2つの理由がある。1つは、金融機関が公的なものであるという認識が強すぎること。そして金融機関が積極的に動くべき組織だという理解が金融機関側にもある。ところがこれは誤解である。 金融機関は受け身の存在である。それは実物経済の生み出した遊休貨幣を、それを必要とする実物世界に仲介する機能を本質とするからだ。 このことを当局も金融機関も忘れている。極端に言えば、地域の金融機関がどう動こうと良くならない経済は良くならない。金融機関は良くなってきた時に手を貸すことしかできない。こういう観点で言うと、産学官協力の地域再生運動に金融機関も参加して「産学官金」でやろうなどというスローガンは考えものである。 実は、リレバンの強化プランの末尾に「推進体制」という項目があり、そこに次のような文言が書かれている。 「当局は、銀行法24条(協同組織金融機関については、同条を準用する規定)に基づき、各金融機関に対し、平成17(2005)年8月末までに、策定した計画について報告を求めるとともに、以後、半期毎に同計画の進捗状況に係る報告を求め、そのフォローアップを行うものとする」 改めて考えてみればリレバン計画の提出、及びその後のフォローアップ(要は進捗状況のチェック)まで法律で行うというのは監督権の拡大解釈である。リレバンは金融機関の業務上の方針、方向性を示すものであり、やるやらないを含めて経営判断に委ねられるべきものだ。 ここまで法律を振りかざせば、これは“要請”でなく強制であり、やらないとひどいことになるぞという脅しである。言葉では「官ではなく民の力で」とか、「個々の金融機関の個性を尊重」、「地域の特性を考慮」と述べているが、本質が権限拡大であることはこの条文を掲げたことに示されている。 金融庁は、2004年の金融改革プログラムの後に「金融検査に関する基本指針」も発表しているが、これを見ると利用者の代表という錦の御旗の下で何でもできるようになっている。場合によっては無予告の検査もあるというのだから、金融機関は恐怖である。 また金融庁はリレバン計画の進捗状況をチェックする際に、分かりやすいようにABCDの4段階評価を導入すると言う。低評価には文句も言えるというが、金融機関と当局の力関係で「意見申し出制度」が有効だろうか。 今回のプログラムでは、中小金融機関が数値目標を出すことも歓迎している。合計586の地域金融機関のうち391機関が、経営相談や取引先企業支援で数値目標を出したという。 リレバン行政を歓迎する論者もいる。信用金庫の預貸比率が2005年3月には57%(1991年は73%)にまで低下したことに象徴されるように、本業での地域貢献度が落ちている現状を改善するには、当局に音頭を取ってもらうのも悪くないという意見だ。しかし、それではあまりにも情けない。 ここで振り返ってほしいのは、この行政の発端は6年前にまでさかのぼるということだ。 事態の発端は99年に金融庁が「金融検査マニュアル」を発表したことにある。この機械的適用によって世に言う貸し渋り不況が生じ、それは「検査官不況」とも呼ばれた。これが世間から批判を浴びて、2002年には「検査マニュアル」の別冊が世に出る。 同年、「金融再生プログラム」が金融審議会の審議を経て決定。それに基づいて2年間の行政指針が示されるが、地域金融機関には大手金融機関とは異なる指針が必要とのことから、金融審議会内にワーキンググループ(WG)が設置される。これが、通称リレバンWGと呼ばれるものである。
2003年の3月にWGの報告が出ると、翌日に「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」が発表される。これに従って8月までに金融機関にリレバン計画の提出が求められた。 この計画は2年間(2003〜04年)限定であった。金融関係者は昨年の暮れ頃、これでおしまい、やれやれと思ったところ、事態は思わぬ方向に動き始める。2004年の12月に「金融改革プログラム」という先の再生プログラムの改訂版が金融庁から発表され、リレバン計画は継続される。これが一方的であったことには証言がある。
「このたびの金融改革プログラムの策定に当たっては、金融審議会等での議論が行われず、経済財政諮問会議、伊藤達也金融担当大臣の私的懇話会、金融庁との間で作業が進められてきました。このため、先のリレーションシップバンキングの議論と異なり、信用金庫業界としての意見を主張する機会を得ることが極めて難しい状況でありました」(平成16=2004年12月24日付の全国信用金庫協会から各信金理事長宛の文書) 金融改革プログラムは金融審議会を飛び越えて、担当大臣から審議会の部会、そしてWGに渡され、ここで体裁を整えることになる。 しかし、これはかなり強引である。旧計画の期限切れに伴って、新計画を起こすということはどこにも書いていないし、2003年のプログラムを読んでも、その改訂については書かれていない。旧では報告書だが新計画では座長メモに置き換わっている。 しかも座長メモが2005年3月28日、新プログラム発表が翌29日と、2年前と同様、年度末の土壇場決定だった。 金融マンにとっては再び不毛の夏休みが訪れた。各金融機関が8月末までの提出を義務づけられたからである。 以上のような経過を見ると、このままでは2年後に新々リレバンが登場する。気がついてみたら、資本金・出資金だけが民間で、行動はほとんど当局が規制することになりかねない。 地域金融機関が自分たちの役割を再認識し金融庁に対抗し得る哲学を持たねば、日本の「金融社会主義」は避けられそうにもない。 (日経ビジネス2005年12月12日号) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||