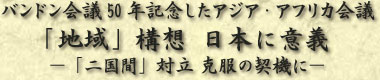|
||||||
|
先週、バンドン会議50周年を記念してインドネシアで開かれたアジア・アフリカ会議は、日本が「アジア・アフリカの一員」だということを思い起こさせる場であった。アジア・アフリカの新興独立国が、植民地主義反対で団結したこの会議が開かれた1955年、「アジア・アフリカ」とは何よりも、西洋の支配から独立を勝ち取ろうとする国々や地域を意味した。ネルー、スカルノなど独立の栄光を担った指導者が集結したバンドン会議は、西洋列強が世界を支配した時代の終焉を鮮烈に知らしめた。 一方でバンドン会議は、戦後日本にとって初の国際会議でもあったが、その立場は微妙であった。参加国は新興独立国という点でこそほぼ共通していたものの、一方にインド、中国など中立主義・共産主義諸国、他方にパキスタンなど親西側諸国と二分されていた。日本招聘は、中国の参加に対抗して、「アジアでの反共最大の大物」たる日本を招くというパキスタンの思惑が背後にあった。 米国はバンドン会議が反欧米感情を結集することを危惧した。そして会議開催を阻止できないと悟ると、フィリピンなど親西側諸国に、会議に積極的に参加してその「左傾化」を阻止するよう求めた。この要望は、鳩山政権下の日本にも伝えられた。 バンドン会議を「アジア復帰」の第一歩としたい日本には、三つの選択がありえた。まず米国の意を受けて積極的に反共を主張する路線である。だが米国の冷戦戦略に距離をおく姿勢は、左右を問わず日本国内で共通していた。また、この路線の「アジア」は、フィリピン、韓国などアジアの親米諸国になる。戦前・戦中に日本から受けた傷のとりわけ深い国々であり、当然に対日感情は厳しかった。 二つ目の選択肢は、インドやインドネシアなど、バンドン会議の中核となった中立主義諸国に同調する路線である。これら諸国はアジアの冷戦緩和を望む点で日本と共通しており、また東南アジアから南アジアへと、日本の「アジア復帰」を大きく広げるものでもあった。だがそれは、戦後日本が米国の「ドルと核の傘」から抜け出る覚悟を要するものであった。 結局日本は第三の道を選んだ。政治的問題になるべくかかわらず、経済問題に力を注ぐ。それは冷戦によって引き裂かれたアジアの一方を選択することを回避する方策であった。経済審議庁長官・高碕達之助を代表に送り、この方針を実践した日本は当然バンドンできわめて影の薄い存在であった。 そして50年後の今回である。日本はおそらく最も巨大な存在感を持つ参加国の一つであった。それは「独立」でくくられた「アジア・アフリカ」が、植民地の消滅によって求心力を失ったこと、他方でアジアが「開発」の時代を経て、何よりも「経済」を軸とする地域に変貌したことを反映している。「独立」との距離を測りかねていた戦後日本は、「開発」と「経済成長」のアジアに迷うことなく参入できた。 半世紀前には「独立」の熱気渦巻くアジア・アフリカと、冷戦で分断されたアジアが日本の眼前を覆っていた。今日、もはやアジア・アフリカを政治的に怜悧に分断するものはない。だが、「先進国の一員」へと猛進した戦後日本は、「アジア・アフリカの一員」をどこかへしまいこんでいた。 今日、「アジア・アフリカの一員」たることは、日本にどのような意味を持つのか。それは何よりも日本が「地域」を考える契機でありうる。戦後日本は対米関係を主軸に二国間関係で世界をとらえ、「地域」を考えることは稀であった。冷戦下ではやむをえない面もあったが、今日、「地域」を構想し、その内実を魅力と説得力をもって描くことが重要課題なのである。 アジアの「経済成長」で主軸となった日本には、次なる段階を構想する責務の一端があろう。だがそれ以上に、「地域」構想のなかに二国間関係の困難を包摂し、豊かな可能性に転化することが可能なのである。厳しさを増す日中関係の生産的な出口は、「地域」を魅力あるものとして構想し、その中に、勝ち負けに陥りがちな二国間関係を包むことでしか見出せないように思う。二国間関係と並んで「地域」を構想することは、多くの実りを日本にもたらすであろう。「アジア・アフリカの一員」たることの「再発見」は、日本にとって地域を構想するまたとない契機なのである。 (北海道新聞夕刊2005年4月28日) |
|||