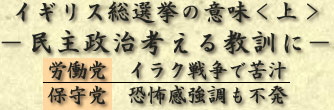|
||||||
|
トニー・ブレアは、選挙に勝利した史上最も不人気な首相として記憶されるであろう。労働党は党史上初の総選挙三連勝という偉業を達成したものの、得票率、議席数ともに圧勝した前二回の選挙とは程遠く、勝利感はまったくないであろう(議席数で47、得票率で5.8ポイント減)。選挙戦では政策論争よりもネガティブキャンペーンが目立った。私は1997年にもイギリスに留学し、ブレア政権の輝かしい出発を目の当たりにしただけに、ブレアの苦境に政治の無常を感じる。しかし、私には、グローバル化時代の福祉や平等という政策課題についても、ポピュリズムを乗り越えるという政治手法の面でも、今回の選挙は、21世紀の民主政治を考える上で教訓に富んだものだったように思える。 労働党の苦戦の原因は、イラク戦争に尽きるといってよい。あの戦争から二年経った今でも、イギリスでは戦争の正当性、合法性をめぐる論争が続いていた。とりわけ労働党支持者の中には、ブレアはブッシュの不法な戦争に荷担したという批判が渦巻いてきた。そして、投票日の一週間前に、これまで政府が一貫して公開を拒んできた機密文書―司法長官が戦争の合法性について疑義を呈したもの―が暴露され、イラク戦争は選挙の大きな争点に再浮上した。 この文書の公開を契機に、ブレアは議会と国民を欺いて、不法な戦争にイギリスを参加させたという怒りが国民の間で沸騰した。イラク問題に限らず、ブレア政権は、少数の取り巻きによる政策決定、野党のみならず与党の一般議員の声を無視した傲慢な政権運営というイメージで捉えられていた。指導者としての政治責任を果たさないブレアを痛い目ににあわせようというムードが選挙戦の終盤で広がった。 しかし、ともかく安定多数を確保できたことは、国民が指導者は誰であれ、労働党政権の継続を望んでいることの表現である。実際、この8年間の政権の下で、経済は安定した成長を続け、雇用や所得も上昇してきた。また、保守党政権時代に削減された医療や教育などの公共サービスに対しても財政資金の投入が進み、改善が実現している。このように、政策面での実績に関しては、国民は労働党に及第点を与えたのである。30年前の、インフレや財政赤字という労働党政権のイメージは払拭され、労働党は政策能力に関する信頼性を獲得したということができる。 そのことの裏側として、ポスト新自由主義時代の保守政治の混迷も今回の選挙で明らかになった。イギリスでは1980年代から90年代前半にかけて、サッチャー政権が小さな政府に向けて、民営化、規制緩和などの政策転換を進めた。しかし、政府は小さければ小さいほどよいというわけではないことをイギリス国民は理解している。保守党の内部にはいまだに小さな政府を信奉する急進派と、公共サービスを重視する現実派が混在し、政府の公共的役割に関して明確なビジョンを示せなかった。そのため、党内をまとめる争点として、移民や難民の規制、治安の悪化、院内感染の増加(医療政策の失敗)などを唱えて政府を攻撃した。オーストラリアやアメリカでは、このような身体的恐怖感をあおるキャンペーンは成功し、保守政権誕生の最大の原因となった。 しかし、イギリスではこの手法は成功せず、得票率は0.5ポイント増にとどまった。イギリスは現に多くの民族からなる多民族国家であることを、保守党は読み誤った。また、多くのメディアもこのような扇情的で非人道的な政策を批判した。結局、保守党は経済社会の運営という大きなビジョンを示せないまま、周辺的な問題について政府の揚げ足を取るというイメージを自らに貼り付けたのである。 民主政治の成熟度について単純な印象批評は避けるべきであろう。しかし、恐怖の政治が不発に終わったことは、今回の総選挙の最大の特徴だと私は考える。また、イラク戦争の開戦に至る経緯を検証し、首相の政治的責任を追及する議論をメディアが継続していることにも、感服する。民主政治の土台の堅固さに思いをいたすばかりである。 |