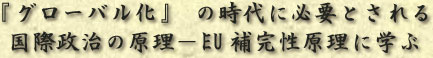|
||||||
|
編集委員:「グローバリゼーション」 「グローバル化」 「グローバリズム」 という用語を用いた本も97年のアジア通貨危機以降多数出版・翻訳され、 マスコミ等でももちいられるようになりました。 遠藤先生は、 「グローバル化」 という現象をどのように把握され、 また 「グローバリゼーション」 という用語をどのように整理されていますか。 遠藤:私は、 社会科学・理念・現実の動きそれぞれの相で、 「グローバリゼーション」 「グローバル化」 という用語の使われ方を見て、 いくつかの混同があると思っています。 第一に 「グローバリゼーション」 もしくは 「グローバル化」 と、 理念としての「グローバリズム」との混同です。 私は 「グローバリゼーション」 のことを、 好むと好まざるとにかかわらずモノ、 ヒト、 カネ、 情報の国境をまたぐ移動が高速化・低価格化する運動の総体だと考えています。 しかし、 一方で、 グローバルに展開する物・資本・市場の動きの広がりに対して一定の対応を行おうとするinstitutionつまり広い意味での制度(権力機構、 ルール、 慣習、 思考方法など)の変化も 「グローバリゼーション」 の動きに含んで考えたほうがいいのではないかと思います。 例えば、 「グローバリゼーション」 に反対する立場の人々は、 物の動きそのものではなく、 その動きのルールやルールをつかさどる組織であるWTOなどに反対をしています。 この場合、 批判の対象としての「グローバリゼーション」は、 経済面での物や資本の動きではなく、 その動きのルールにかかわる組織やルールといったものにまでも批判が向けられているように思います。 このような現象を考える上でも経済の運動としての 「グローバル化」 という状況には、 その運動に対応する機構やルールなどを含めて整理する必要があると、 私は考えます。 またそれとは別に、 理念としての「グローバリズム」というものがあります。 この考え方は古くからあるもので、 「地球市民」 とか「宇宙船地球号」といったような広い意味での世界市民連帯の理念を表現している考えだと思います。 原理的には、 「グローバリズム」 の思想つまり世界市民・地球市民の連帯思想の立場から、 「グローバリゼーション」 の実態 (例えば経済的格差の拡大) が批判されることはあります。 つまり必ずしも 「グローバル化」 を肯定する思想として 「グローバリズム」 があるのではなく、 むしろ理念としての 「グローバリズム」 と 「グローバリゼーション」 とは、 区別をして考える必要があるのではないでしょうか。 「グローバル化」 を考える際の二番目の混同は、 「グローバル化」 と 「アメリカ化」 との混同です。 この二つを混同する立場の場合、 「グローバル化」 はアメリカの帝国主義の展開過程として考えられているようです。 しかし、 この二つの側面は―確かに国際政治の面でシンクロする部分はあるのですが―かならずしも同意ではありません。 例えばジョセフ・ナイ氏が 『アメリカへの警告―21世紀の国際政治のパワーゲーム』 という本の中で指摘していますが、 確かに冷戦終結後の世界秩序が変化する中アメリカを中心とした国際政治・軍事面での一極支配化という現象が表面化したと思います。 しかし、 このような状況の中、 アメリカには1年間に4億7000万人が流入し、 物の面では1億2500万台の車の入荷が、 また2100万船積貨物の入荷が行われます。 アメリカ自体が 「グローバル化」 というものにさらされているわけです。 皆さんご存知の2001年9月11日に行われたテロは、 まさにこのような 「グローバル化」 によって流入した人々に紛れ込んだテロリストによって行われたわけです。 アメリカの国際政治面や軍事面での一極集中―いわゆる「帝国」―と、 「グローバル化」 という現象とが同時に起こっている時代を、 我々は生きてるのだと思います。 それからもう一点 「グローバル化」 を論ずる際に指摘しておきたいのが、 「グローバル化」 は、 歴史的にはまだ発展途上―未成熟な現象であるということです。 あれだけ世界を騒がせた97年アジア金融危機の前年、 96年時点で途上国への金融や資本移動量は、 世界全体の三分の一しかないといわれています。 のこりの三分の二は先進国での移動です。 また、 その途上国の経済的な移動のうち特定の途上国に対する移動が四分の三を占めているのです。 そうすると経済のグローバル化といっても、 まだまだその広がりの点では未成熟といえるでしょう。 途上国内でもアフリカやその他いまだ、 グローバル化の影響がまだ十分に及んでいない国があるというのが現状だと思います。 とすると、 我々はこれからさらにグローバル化が進展してゆく状況をイメージしておいた方がいいのではないでしょうか。 編集委員:「グローバル化」 がおこっている時代では、 どのような政治上の問題が起こるのでしょうか。 遠藤:「グローバル化」 という状況は、 今後ますます広がり進展する現象だと思います。 我々は、 「グローバル化」 の流れをみとめざるを得ないでしょう。 ところで、 政治的にみていくと、 「グローバル化」 が進む中で、 近代以降国際政治の主体であるとされた国家体制そのものが、 経済の流れに揺さぶりかけられるという状況があります。 国家主権、 あるいは近代の国家中心の政治機構を中心にする考えをエタティスム (tatisme=国家中心主義) とすると、 そのような枠組だけでは対応できない問題が 「グローバル化」 によってもたらされてくるのが現在なのではないでしょうか。 広い意味でのエタティスムの枠組みは、 「民族自決」 という考え方も融合していますが、 このような考え方では、 アジアの金融危機のような場合は対応できない。 「グローバル化」 が進む時代においては、 エタティスムや民族自決の原則に変わる新たな統治・政治のルールが必要になるのではないでしょうか。 編集委員:先生が御専門にされているEU (ヨーロッパ共同体) もグローバル時代の国際政治における 「新たなガバナンス」 のあり方として考えていいでしょうか。 遠藤:新たな取り組みの一つであると思います。 ヨーロッパは70年代に社会民主主義勢力が躍進しましたが、 オイルショック以降低成長と財政赤字により、 その勢力は岐路に立たされることになります。 とくに80年代にはその傾向が強くなっていきます。 このような状況の中、 例えばフランスでは、 ミッテラン政権が1983年にそれまでの2年にわたる一国ケインジアン的政策を否定し、 フランを特にドイツマルクに対して切り下げ資本流出を防ぎ緊縮財政を中心とした経済政策の大転換を経験します。 この経験から、 ヨーロッパの左翼政権は、 経済における相互依存関係を、 不可避の政治課題として認識せざるを得なくなったのではないかと私は考えています。 この後、 ヨーロッパではECにおける市場統合ブームがおとずれ、 ヨーロッパ内の自由貿易を進めるというネオ・リベラル的な側面で統合が議論され、 さらに後には通貨統合という議論がヨーロッパの域内政治の課題として取り組まれることになります。 この市場・通貨というヨーロッパ大の政策資源の枠内で、 ヨーロッパの社民政権は90年代の後半までに、 欧州社会憲章などの 「弱者保護」 のイニシアティブも実現してきました。 通貨続合は画期的なことです。 というのも、 政治学の伝統ではジャン・ボダンがいうように通貨発行は国家の基本要件に属するものとして考えられてきたからです。 それとともにこのEUの経験は、 経済面で 「グローバル化」 に対し、 加盟国同士で域内統一通貨市場を中心としたある種の抵抗力を持ち、 それとともにに政策をすすめるという、 社民政権のスタンスの変化ないしは成熟なしには考えられないのではないでしょうか。 こうしてEUは、 「グローバル化」 の時代におけるヨーロッパの政治的な資源として新しい統治のありかたを受容れてきたのです。 編集委員:具体例として、 EUや通貨統合が国際政治におけるヨーロッパのあり方にあたえた変化を示す事例はありますか。 遠藤:例えば、 現在ポルトガル政府は、 ヨーロッパの中では放漫財政を行っています。 もしポルトガルが一国で通貨運営していたら、 どのようになるでしょうか。 かつて、 90年代初頭、 イギリスは投資家にポンドを狙い撃ちをされ経済面での大混乱をきたすという事態を経験しています。 しかしポルトガル一国の経済もヨーロッパの統一通貨ユーロに結び付けられている以上、 投資家は一国の通貨を狙い撃ちしにしてその国の通貨を短期に交換して利益を得るというような投機を行うことはできません。 もし行おうとすればヨーロッパ全体の金融市場や資本市場を相手にしなければならない。 ポルトガルの事例は、 EUに加盟し統一通貨を用いることで、 「グローバル」 な市場に対して、 結果として小国が一定の対抗力を持ちうるという例だと思います。 またフィンランドの事例をお話しましょう。 かつてアメリカは、 フィンランドがEU加盟前その基幹産業であるパルプ産業をアンチ・ダンピングでねらい打ちした時期があります。 しかし、 フィンランドが一旦EUに加盟してしまうと、 「帝国」 アメリカに対し、 一定の抵抗力をもてるということです。 国際政治におけるアメリカの一極化に対して、 EUが独自の意味を持っているということを示す事例だと思います。 以上の例は、 「グローバル」 な経済的・政治的状況を、 ナショナルに解決するということではなく、 ある種の相互依存関係を基盤にした多国間統治体制に加盟することで、 打開している事例だといえましょう。 編集委員:このようなEUの多国間統治体制には基本的原理があるのでしょうか。 遠藤:EUの補完性 (Subsidiarity) 原理という基本理念に、 私は注目をしています。 補完性は―今年の雑誌 『思想』 1月号にも書いたのですが―近世初期にまでさかのぼれる政治原理です。 この原理は、 幾多の歴史を経て鍛えられたものであり、 特に大きな機構によって全体を統治しなければならないような政治的解決が必要な時代に注目されてきた考え方です。 この原理は二つの原理から成り立っています。 「政治的に小さな存在が自ら目的を達しうることに関しては (国家のような) より大きな機構は介入してはならない」 これが第一原理です。 しかし、 第二原理では、 「小さな存在が対応できない問題に対しては、 より大きな機構は (積極的に) 介入しなければならない」 となっており、 問題が小国で解決できないときにはむしろ、 より大きな統治機構による問題解決の妥当性を主張するものです。 現在この原理は、 EUと加盟国間の関係に適用されています。 「グローバル化」 という大きな社会変化をうながす現象に揺さぶられる過程で、 ヨーロッパでは再び、 補完性原理という歴史的な政治原理を現代によみがえらせたのです。 編集委員:日本やアジアの場合にもEUのような多国間連携の可能性はあるでしょうか。 遠藤:問題意識としては非常に重要な視点だと思いますが、 現実問題としては難しいと思います。 EUとアジア圏との戦後の発展の歴史を比較していくとその難しい面が理解しやすいと思います。 まずEUの場合、 安全保障の面―つまりNATO加盟国での多国間連携と、 ECなど経済面での連携が、 一致しながら進んできたという経緯があります。 戦後冷戦の枠組では、 西側諸国を中心とした二つの側面での条約機構が中心であり、 冷戦体制崩壊後は徐々に東欧圏を吸収しつつ拡大してきました。 この過程でも安全保障の枠組拡大と経済圏の拡大とがほぼ一致しながら、 パラレルに進行しているわけです。 安全保障と経済の両方での連携が進んだことで、 比較的共通のルールを構築することが安定的に行えたという面は、 ヨーロッパにはあったと思います。 ところが、 アジアでは安全保障と経済圏という二つの側面は、 まったく異なる状態にあります。 経済圏においては、 地域内フリー・トレード構想は、 中国を中心としたものも、 日本を中心としたものも存在し、 実際に中国=ASEANや日本=シンガポールなどとの間では実現に向けて連携が進んでいます。 しかし、 安全保障の面ではどうでしょうか。 東アジアでは、 戦後、 安全保障体制はアメリカを中心として形成されてきた経緯があります。 一方で中国や北朝鮮は、 安全保障の面でアメリカに対抗する勢力として存在しています。 ですが経済面で見ると中国は、 アジアにおいて非常に重要な位置を占めています。 中国を抜きにしてアジアの経済は語れなくなってきています。 97年のアジア金融危機以降経済問題を中心とした多国間連携が少しずつ実現する一方で、 安全保障面での多国間機構が形成できないという点で、 EUとアジアでは政治的に異なる状況にあるといえるでしょう。 それから重要なのは、 日本はドイツのように戦後処理を徹底して行った国ではないし、 中国もまた、 フランスのように 「人権の生みの親」 ではない、 ということです。 ヨーロッパにおいて、 ドイツやフランスは影響力のある国ですが、 この両国の連携の背後には、 多国間連携の際に必要な理念―例えば人権というような基本理念が共有されていたという事実がありますが、 中国に同じレベルのコミットメントを求めるのは、 残念ながら現在のところ困難であると思います。 もう一つ付け加えておくならば、 アジア諸国は、 いまだにネイション・ビルディングの途上にあるという点があります。 大半の国は戦後脱植民地化という課題に対応する中で自国の国家機構を整えてきました。 ヨーロッパの国家機構と比較すると、 今だその完成に向けて途上にある国が多いのではないでしょうか。 以上のような点を比較して見ると、 ヨーロッパ型の多国間連携を東アジアに適用することは難しいのではないでしょうか。 ただ、 EUのようなヨーロッパモデルが多少なりとも妥当性をもつとすると、 現代は、 「グローバル化」 のような国家の枠組を超えた課題に応えなければならない時代であるということ、 そしてその課題に答えるために非主権的な解決策を意図的に行って対抗しているということにあります。 これらの点に関してはヨーロッパの手法が先駆的であり、 学ぶべきところがあるのではないかと、 私は考えています。 編集委員:「グローバル化」 の時代において国際政治で先生が注目されているポイントは何でしょうか 遠藤:私は現代を、 「グローバル化」 によって統治機構とその対象が流動化する時代、 として考えています。 国家中心的なアプローチだけでは、 現代の政治課題は解決できません。 しかしこのことは、 国家の否定ではなく、 国家の限界を前提にした新たな統治を創造していく時代に入ったともいえるでしょう。 EUのような多国間統治体制は、 この意味において、 壮大な実験の成果だと思います。 共同で編んだ 『グローバル化時代の地方ガバナンス (岩波書店・近刊)』 では、 現在日本においても、 都道府県レベルの行政組織が公共事業の落札などでWTOの規制のもとにあることが確認できると思います。 日本においても地域レベルで 「グローバル化」 の影響を受けていると考えていいでしょう。 それから、 NPOなどの組織との連携といった市民セクターとの 「協働」 も、 今後 「グローバル化」 によって行政機構が揺さぶられる中で重要視されていくのではないでしょうか。 編集委員:最後に院生へのアドバイスがなにかあればお願いします。
遠藤:まず世代的なものなのかもしれませんが、 精神的に弱い院生が周りに増えているような気がします。 最近の学生を見ていて感じているのが、 大学に出て来なくなった人はなかなか論文をかけなくなるということですね。 ですから院生に何かメッセージを送るとすると、 「粘り強さ、 タフたれ!」 ということを伝えたいです。 何度批判されることがあってもへこたれないようなことが、 研究を行う上でも必要だと思います。 留学ですか?準備から新しい生活への適応などあらゆる場面でタフネスさが要求されるという意味では自分の世界を拡げるいい契機になるかも知れませんね。 タフネスというのは、 限界を感じたときにみんながっかりしたりすると思いますが、 そこで限界がわかったときに自分の殻を破ってそこを突破することを快感として感じられる粘り強さもしくは楽観性のようなものです。 これは研究を続ける上でも社会に出てからでも、 将来的には力として必要になることだというふうに考えてもらえればいいのではないでしょうか。 あとは教官を鏡にしたり壁うちの相手にしたり活用しながら自分の世界を作っていって欲しいと思います。 だんだん説教臭くなっていきそうなのでこの辺で (笑)。 (研究交流誌2003年3月号) |
|||